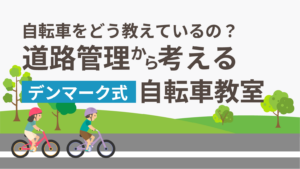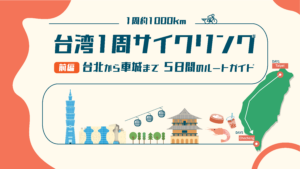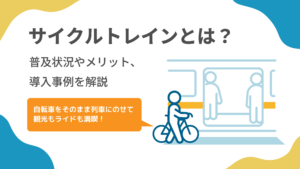レンタルサイクルとは、観光案内所や宿泊施設、民間のサイクルショップなどで自転車を借り、自由に街巡りができるサービスです。
本コラムでは、レンタルサイクルの利用動向や役割、シェアサイクルとの違いと今後の可能性について解説します。ビジネスの視点を交えつつ、観光におけるレンタルサイクルの“今”を探ってみましょう。
レンタルサイクルの運営主体
レンタルサイクルとは、観光客や市民が一時的に自転車を借りて利用できるサービスです。提供主体は、大きく自治体運営型と民間運営型に分かれます。自治体運営型は、市町村や観光協会が地域振興策として自転車を所有し、観光案内所や駅前施設などで貸し出す形態です。
利用料が無料またはリーズナブルな価格に設定されていることが多く、地域住民ボランティアが運営を手伝うケースもあります。
一方、民間運営型はサイクルショップやレンタカー会社、宿泊施設などが自社サービスとして自転車貸出を行うものです。こちらは電動アシスト自転車やスポーツバイクなど多彩な車種を用意し、有料で貸し出す形が一般的です。
レンタルサイクルの利用動向

レンタルサイクルの主な利用者は観光客ですが、その内訳を見ると日本人と外国人で行動に違いが見られます。大阪工業大学の調査によれば、観光地でレンタサイクルを利用する際、日本人旅行者と外国人旅行者では回遊ルートや滞在時間に差異があることがわかりました。
外国人は言語や地理のハードルもあって保守的な移動パターンになりやすく、日本人より移動距離が短めでもあります。平均移動距離は日本人24.1km、外国人22.1kmです。
このため、さまざまな施設への訪問を促すには、おすすめコースの提示や多言語マップの提供など工夫が重要とされています。
参考:大阪工業大学「観光地におけるレンタサイクル利用者の回遊行動分析-日本人観光客と外国人観光客を比較して-」
レンタルサイクルの料金体系
レンタルサイクルの料金体系は提供者によって異なりますが、一般的な相場として1日あたり500〜2,000円程度が多いようです。安価なところではママチャリタイプで1日500円、電動アシスト自転車やスポーツバイクでは1日1,500〜2,000円前後といった料金体系が一般的です。
時間貸しの場合は1時間あたり200〜500円程度、半日パックなどを設ける事業者もいます。自治体運営の場合、観光客誘致の目的から無料〜数百円程度の破格の料金設定をしているケースもあります。
観光地でのレンタルサイクルの役割

観光地におけるレンタルサイクルの役割は、大きく2つあります。1つは観光客の移動手段としての利便性向上、もう1つは環境に優しい交通手段の提供です。
レンタルサイクルを利用すれば、徒歩より広い範囲を効率良く回れますし、バスやタクシーではアクセスしづらい場所にも自力で行けます。特に市街地がコンパクトな城下町や離島などでは、自転車が最適な移動手段となるでしょう。
たとえば金沢市では、主要観光スポットを巡回する観光バスに加えてレンタサイクルが用意され、観光客は自分のペースで城下町を散策できるようになっています。交通渋滞の緩和やCO₂排出削減といった効果も期待でき、自治体にとっては観光と環境両面にメリットのある施策です。
自転車の台数とエリア展開の傾向
都市部の観光地では数百台規模で自転車を保有するケースもあります。たとえば、京都市内の主要レンタサイクル事業者数社を合計すると、貸出可能な自転車は数千台にのぼり、繁忙期には早朝から貸出所に行列ができるほどの人気となっています。一方、地方の小規模な観光地では数十台程度で運用するケースも珍しくありません。
エリア展開としては、駅周辺や観光拠点に貸出・返却拠点を置くのが基本です。利用者がアクセスしやすいよう、道の駅やホテルなどに貸出拠点を設ける取り組みも見られます。
愛媛県のしまなみ海道では、各島に拠点があるほか、富山市や金沢市などでは市内の観光スポット近隣に複数のサイクルポートを用意し利便性を高めています。
ただし、レンタルサイクルは基本的に「借りた場所に返す」が原則です。そのため、観光客は出発地点に戻ってくる必要があります。
レンタルサイクルとシェアサイクルの違い

近年、普及が進むシェアサイクルとの違いは「乗り捨て」できるかどうかです。シェアサイクルは借りた場所とは別のポートで返却できるのに対し、レンタルサイクルは基本的に借りた店舗・場所に返却する必要があります。
そのため、シェアサイクルは短距離の移動を小刻みに乗り継ぐのに適し、レンタルサイクルは借りた自転車を一日占有して自由に移動できるのがメリットです。
観光スタイルによって向き不向きがあり、例えば「午前中に観光地Aを見て午後にBに移動する」というプランならシェアサイクルが便利です。一方「一日じっくり街全体を散策する」場合はレンタルサイクルでずっと同じ自転車を使う方が荷物の管理なども含め楽でしょう。
また、シェアサイクルはGPS搭載のスマートロック付き自転車を使い、アプリ決済により無人で貸出できます。
レンタルサイクルは人手で貸出・回収を行うケースが多いですが、トラブル時にスタッフに相談できるメリットがあります。一方で営業時間が限られる、人件費がかさむ、といった課題は残ります
まとめ|レンタルサイクルの今後の展望
レンタルサイクルは単に自転車を貸すだけでなく、地域の体験を提供する媒体としてさらなる進化が期待できます。たとえば、貸出時におすすめの観光ルートデータをスマホに転送したり、AR技術で走行中に観光案内が受けられるサービスなどが実現すれば、観光客の満足度向上につながるでしょう。
人手を介するレンタルサイクルはコスト高になりがちです。そこで、ICカードやスマホを使った無人貸出システムの導入や地域企業からのスポンサー協賛などによる収入確保などの工夫が重要です。
また、観光DXの一環としてレンタサイクルの利用者属性や行動経路などのデータを収集・分析し、都市計画やマーケティングに活用するといった展望もあります。
実際、さいたま市ではシェアサイクルの利用データを活用して街の移動傾向を分析し、脱炭素化施策に役立てる実証が進められています。レンタルサイクルでも同様に、得られたデータから観光客の行動パターンを把握し、地域の観光戦略にフィードバックする取り組みが期待できるでしょう。