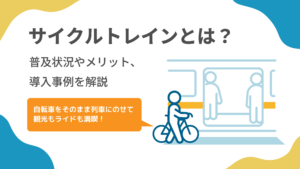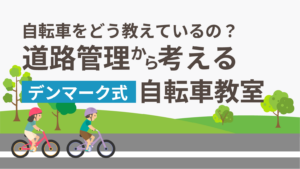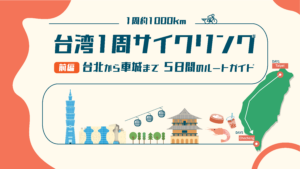近年、日本各地の主要な観光地でシェアサイクルの導入が進んでいます。移動の利便性を高め、観光客の回遊を促す取り組みとして注目され、HELLO CYCLINGやドコモ・バイクシェアなど大手企業も積極的に展開しています。
本コラムでは、観光地シェアサイクルの現状や観光促進への効果、課題について詳しく解説します。
観光戦略として広がるシェアサイクル

日本でシェアサイクルが導入されたのは2005年の東京都世田谷区が最初で、その後、導入自治体が増加しました。
2019年3月末時点で約225の都市に導入されており、国土交通省の調査によれば導入目的で最も多かったのは「観光戦略の推進」でした。政府もシェアサイクルを公共交通機関の補完や観光客の利便性向上につながる施策として支援しており、「観光立国」に向けた地域活性化のツールとして期待されています。
参照
公益社団法人日本都市計画学会「観光都市へのシェアサイクル導入が観光客の立ちより施設数と滞在時間に与える営業-神奈川県鎌倉市を対象として-」
国土交通省「シェアサイクル公共的な交通としての在り方について」
主要なシェアサイクル業者
シェアサイクル事業は官民さまざまな主体によって運営されていますが、中でもシェアが高いのがHELLO CYCLING(OpenStreet社運営)と、NTTドコモ子会社のドコモ・バイクシェアです。
HELLO CYCLINGは電動アシスト自転車を主力とし全国で約350万の会員ユーザーを抱え、2024年時点で全国に約8,500か所のポート(貸出拠点)網を整備しています。
ドコモ・バイクシェアは東京都心部や政令市中心部を中心に展開し、多くの自治体と連携してサービスを提供しています。
その他の主なシェアサイクル運営会社

観光促進にもたらす効果
シェアサイクルを導入する最大のメリットは、観光客の行動範囲が広がることです。実際に、鎌倉市を対象にした研究では、シェアサイクルを使うことで観光客が訪問できるスポット数が増加することが明らかになっています。徒歩や公共交通だけの場合に比べ、自転車を併用するとより多くの場所に立ち寄れるためです。
つまり、シェアサイクルは滞在時間を維持しつつ、観光スポット巡りの数を増やせるツールと言えます。自転車でならアクセスできる隠れた名所もあり、シェアサイクルが潜在的な観光資源の発掘につながる可能性もあります。
たとえば、広島市のコミュニティサイクル「ぴーすくる」では、サービス開始10年で年間利用回数が100万回を超える規模に成長し、観光客が自転車で市内各所を回遊する姿が定着しました。
従来は訪問者が少なかったエリアにも人の流れが生まれ、地元商店の利用機会増加など地域経済の活性化効果も報告されています。
シェアサイクルの成功事例
日本全国では様々なシェアサイクルサービスが展開され、地域特性に合わせた独自の発展を遂げています。大手企業から地方自治体との連携まで、各地の特色ある成功事例をご紹介します。
HELLO CYCLING

画像引用:OpenStreet株式会社
HELLO CYCLINGはソフトバンク系列のOpenStreet社が運営するシェアサイクルサービスで、主に郊外や住宅地を中心にポート網を広げてきました。電動アシスト自転車による快適な乗り心地と、アプリで完結する手軽な利用方法が強みとなり、国内最大の会員数を誇っています。
成長スピードは驚異的で、2017年3月末には約1,200箇所だったポートが、2024年3月末には約21,000箇所に達する見通しです。この急成長は、自治体や企業との連携による全国展開が成功した結果といえるでしょう。
参照:SoftBank News「Japan’s Bike-sharing Leaders Collaborate to Increase Customer Convenience」
ドコモ・バイクシェア

画像引用:株式会社ドコモ・バイクシェア
NTTドコモの子会社が運営するドコモ・バイクシェアは、東京23区や横浜市など大都市中心部での展開に強みを持っています。各地の自治体と協定を結び、「○○シティサイクル」といった地域ブランド名でサービスを提供するケースが多く、広島市の「ぴーすくる」や札幌市の「ポロクル」も実質的にはドコモがシステムを提供しています。
すべての自転車に電動アシストが付いているため、観光客でも坂道の多い土地を楽に巡ることができるよう配慮されてるのが特徴です。2025年度中にはHELLO CYCLINGとの提携によりポートの相互共有が始まる予定で、将来的には単一のアプリで全国どこでもシェアサイクルが利用できる時代が訪れる可能性があります。
ポロクル

画像引用:特定非営利活動法人 ポロクル
北海道札幌市の「ポロクル」は、2012年に日本初のNPO運営型シェアサイクルとしてスタートしました。現在では市中心部に約60か所ものポートを設置する規模に成長しています。
坂の多い札幌に合わせて全車電動アシスト自転車を導入し、雪国という環境下でも春〜秋にかけて安定した利用実績を上げています。観光シーズンには英語対応も行い、外国人観光客の利用も拡大しました。
ぴーすくる(広島)

画像引用:株式会社ドコモ・バイクシェア
広島市の「ぴーすくる」は平和都市ヒロシマにちなんだ名称で、2015年の本格導入以降、順調に利用者を増やしてきました。開始当初は広島駅や原爆ドーム周辺など14か所のポート・約150台の自転車でスタートし、画期的だったのは通信機能付きスマート電動自転車を採用した点です。
これにより大がかりな専用機器が不要となり、狭いスペースにもポートを設置できるようになりました。運営はドコモ・バイクシェア社が担い、自治体との官民連携でサービスを提供しています。利用目的の約半分は通勤通学など市民による日常利用ですが、残りは観光客で占められており、双方のニーズをバランスよく取り込んだ成功例といえます。
シェアサイクルを運営する上での課題

シェアサイクルにはまだ課題も残されています。まず情報提供と利用環境の課題です。大都市ではスマホアプリで直感的にポートや空き台数がわかりますが、地方の観光地では必ずしもそうとは限りません。
自治体や観光協会が個別に運営するケースが多く、レンタサイクルの案内情報が市役所サイトや観光協会のページ、配布チラシなどに分散しがちです。
その結果、「自転車を借りたいけどどこで借りられるのかわからず諦めてしまう」という観光客も見受けられます。観光客にとって使いやすいよう、現地での案内標識の充実や、多言語対応を含めた情報発信の一元化が求められています。
また、観光客がどこを巡れば良いかわからないという課題も指摘されています。シェアサイクルは気軽に借りられる反面、現地でルート相談できるスタッフがいないのが一般的です。
貸出時に地図や観光案内が得られる従来型レンタサイクルと異なり、初心者の観光客には適切なコース選びが難しい場合があります。その結果、主要スポットだけを回って満足して終わり、リピート利用につながらないケースも。
この対策として、アプリ上でおすすめルートを提示したり、GPSデータを活用して他の利用者の人気コースを可視化するなどのサービスが期待されています。実際、HELLO CYCLINGのアプリでは観光スポット巡りを促すデジタルスタンプラリー的な機能の実証も行われています。
まとめ|シェアサイクルの今後の展望
全国の観光地に広がるシェアサイクルは、観光客の新たな移動手段として根付きつつあります。歩きや公共交通機関だけでは得られない自由な旅ができ、地域内の回遊性向上や経済効果を生み出す可能性を秘めています。
これからは事業者間の連携で、「どこでも同じように使える」全国的なシェアサイクル網ができるかもしれません。そうなれば、旅行者はアプリ一つで日本中の観光地を自転車で巡れるようになり、旅の自由度が大きく広がるでしょう。
シェアサイクルは今や観光インフラの一つと言えます。自転車で地域の魅力を再発見できるこの仕組みを、長く続く形で定着させていくことが大切です。